体験談:コピーソフトを使う職場にいた私の葛藤と後悔!違法ソフトのリスクも解説
バックオフィス業務ではパソコンを使うのが当たり前の時代、事務職で働いているとさまざまなソフトを使用します。
一般的なのはワープロソフト(Wordや一太郎)、表計算ソフト(ExcelやGoogleスプレッドシート)、メールソフト(OutlookやGmail)あたりでしょうか?
プレゼン資料の作成にPowerPointを使ったり、会計ソフトや電子回覧ソフトを使ったりすることもあるでしょう。
それらソフトの多くは利用に際してライセンス契約が必要であり、契約台数を超える数のパソコンへのインストールはできません。
フリーソフトならばこの限りではありませんが、専門性の高いソフトを利用するには費用がかかり、数万円、数十万円するソフトも存在します。
業務に必要なソフトを揃えるには、それなりの費用がかかるわけです。
だから、費用を抑えるために違法なコピーソフトを利用する職場も存在します。
実は、事務たぬきがかつて働いていた職場でも、コピーソフトは使われていました……。
この記事では、そんな実体験を交えつつ、違法なコピーソフトを使うリスクと見つけたときの対象法を書くことにします。
かつての職場でコピーソフトの利用が常態化していた理由
事務たぬきはかつて、小さな家族経営の会社で事務員をしていたときがあります。
家族経営といっても、そんなにべったりとした人間関係でもなく、良い意味でアットホームな、居心地の良い職場でした。
薄給でしたが残業はほぼなく……業務が立て込んでいない時期は、合間に資格試験の勉強をする余裕もありましたね。
そんな良い感じの職場だったのですが、一つ気になることがありました。
それは、業務で使用するソフトが、正規版を購入してインストールしたものではなかったことです。
入社時からそれは常態化しており、暗黙のルールとでもいいましょうか……「それが当たり前」という風潮でした。
違法ソフトの利用が常態化していた理由は、主に次の3つです。
- 経営者がコピーソフトの違法性を理解していなかった
- 零細企業で正規版のソフトを購入する予算がなかった
- 誰も強く指摘できない雰囲気だった
不正ソフトの使用リスクについて意識を高め、ライセンスコンプライアンスを推進している「Business Software Alliance」(ビジネス ・ソフトウェア・ アライアンス/頭文字を取って略称はBSA)という組織があるのですが、私はBSAが言うところの「知財ブラック企業」にいたことになるとのちに知りました。
「知財ブラック企業」とは?
違法コピーやライセンス違反のソフトを使わせるなど、第三者の知的財産権侵害が常態化している企業や団体を「知財ブラック企業」と呼んでいます。
理由はなんであれ、やはり不正コピーしたソフトの利用は違法行為です。
「これって良いのかな」
「いや、良くはないよな」
「てか、ダメだよな……」
……というように、当時の事務たぬきも思っていたのですが、何も言い出せず、何もできませんでした。
結局、その時に勤めていた会社は、違法ソフトの使用とは関係なく、さまざまな不運が重なって倒産することになるのですが……。
経営者がコピーソフトの違法性を理解していなかった
社長やその周りの経営陣がみんなITに弱く、関係先の中小・零細企業も同じような雰囲気でした。
そのため、コピーソフトの違法性や使用リスクを正しく理解していなかったように思います。
悪い意味でおおらかだったんですね。
「正式購入したやつじゃないけど、使えるんだから、まあいいじゃないか」という、雰囲気がありました。
「○○さんのところも同じようにやっているし」という、ルール違反もみんなでやっていると問題意識が薄れるのでしょう。
だから、「コピーソフトを使って良いんですか?」と、それとなく聞いてみても、真剣に受け止めてもらえない状態でした。
零細企業で正規版のソフトを購入する予算がなかった
コピーソフトを使っている職場でしたが、業務で使うすべてのソフトが違法なものだったわけではありません。
WordやExcelなどは、パソコンの購入時に正規版をセットで導入しているようでしたし、会計ソフトや積算ソフトはきちんとライセンス契約したものが使われていました。
ただ、違法コピーしたソフトだけは、正規版を購入・契約するのが非常に高価なものだったんです。
それも、誰か一人だけ使うものではなく、使用者が複数人居るため、正規版を人数分揃えるにはかなりの金額が必要でした。
勤め先は家族経営の零細企業。
それなりに仕事の受注はあり、給料もきちんと支払われていたのですが、使用者全員に正規版ソフトを購入するには予算が不足する状態だったようです。
予算はないけれど、業務で使いたい高額なソフトがある。
そのソフトがあると、業務が捗るし、何なら不可欠なものだ。
そんなとき、コピーソフトが手元に回ってきたら……これを使えば、みんなが幸せになれると誤解する可能性は非常に高いでしょう。
違法性を感じても、業務に欠かせないものだと手を伸ばしてしまう、企業のコンプライアンスが問われるところです。
誰も強く指摘できない雰囲気だった
経営者の知識不足と会社予算のことは、職場内の全員が知っていることでした。
だから、同じ職場で働くほかの人たちも、コピーソフトの利用に対して強い問題意識を感じて、指摘する雰囲気はありませんでした。
家族経営の零細企業にありがちな「なあなあ」な空気感が、悪いほうに働いていたともいえるでしょう。
だから私も周りに流され、強く指摘することなく時間が過ぎていきました。
今の自分だったら……BSAの報告窓口に通報したかもしれません。
でも、当時はそういった組織の存在や外部窓口への通報について知識がなく、穏やかに働ける職場環境を壊したくない気持ちが強かったのを覚えています。
コピーソフトを使う職場にいた私の葛藤と後悔
かつて、コピーソフトを使う職場にいた事務たぬきですが、ソフトウエアの不正コピーや違法コピーを肯定するつもりはありません。
ただ、当時は私自身も知識不足・認識不足だったこともあり、経営者に強く言えない立場でした。
でも、時折考えることがあります。
もしもあのとき、違法なコピーソフトの利用が然るべき機関に見つかり、職場が何らかの処分を受けていたなら……自分も不利益を被ったかもしれません。
もっと、適切な対応をしておいたほうが、のちのち良かったのではないかとも思います。
ちなみに、なぜ職場で使われているソフトが、違法なコピーソフトだと気づいた経緯は、操作を覚えるためにソフトのマニュアルが見たいと、職場の方に聞いたんですね。

このソフトのマニュアルって、どこにありますか?
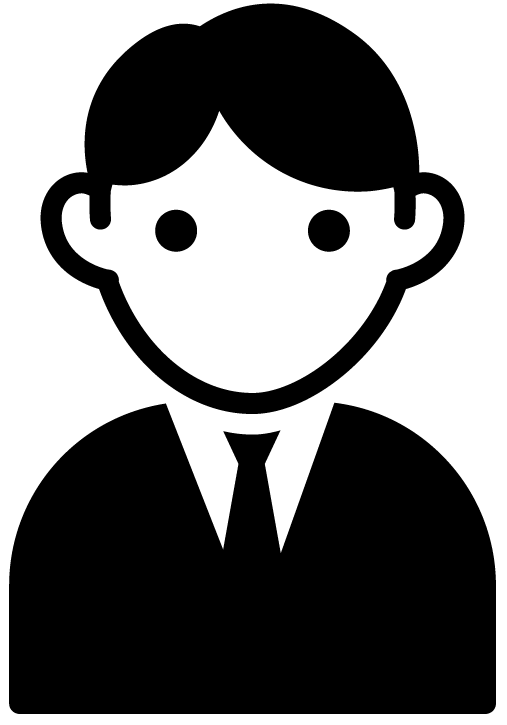
マニュアル? ないよ

ない……?
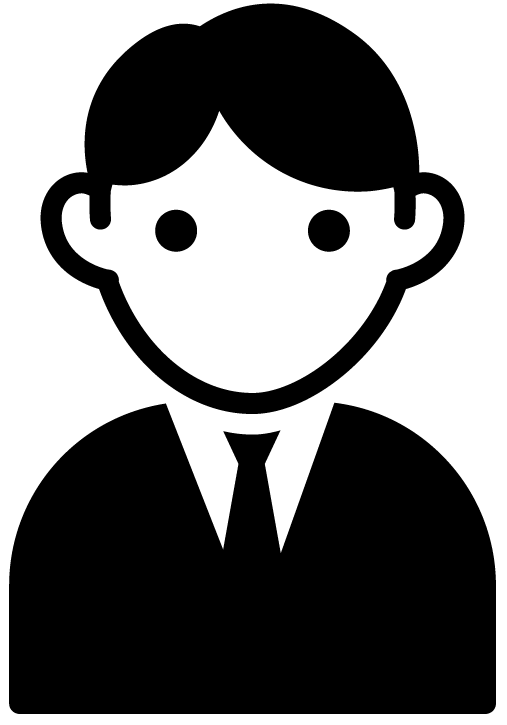
××さんのところで、コピー版をもらってインストールしたやつだから

コピー……??? もらった?????
頭の中は「?」だらけになりつつ、詳しく聞くと、どうも何処かから入手したコピーソフトをインストールしているらしく、社内で使っている同じソフトの出所は全部「そーゆーこと」だと判明。
以来、心の何処かでモヤモヤしたものを抱えつつ……
でも、先述の事情から、コピーソフトの利用について強く言えず……
ずっと、問題から目をそらしてきました。
コピーソフトを利用する企業のリスク
さて、葛藤や後悔がありつつも、一時期はコピーソフトの利用を受け入れてしまった事務たぬきです。
ここからは、あらためてコピーソフトを利用する場合、企業はどのようなリスクを負うのかを解説します。
著作権侵害で損害賠償や刑事罰を受ける法的なリスク
ソフトウエアには知的財産権があり、違法なコピーソフトは知的財産権の侵害に該当します。
知的財産権とは
知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。
ソフトウエアの違法コピーや、そうしたコピーソフトの利用は、著作権法の違反として罰則を受ける恐れがあります。
著作権法 第八章 罰則
第百十九条
著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
法律の条文は記述が読みにくいのですが、ザックリいうと違反した人は10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられるということです。
また、違反したのが法人の場合も罰則が定められています。
著作権法 第八章 罰則
第百二十四条
法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百十九条第一項若しくは第二項第三号から第六号まで又は第百二十二条の二第一項 三億円以下の罰金刑
違反した企業に対しては、3億円以下の罰金を科すとされています。
「見つからなければ大丈夫」「周りもやっているのだから……」などと考える方もいますが、摘発され、訴訟案件となった事例が存在しています。
秋田地裁、「ヤフオク!」での違法複製プログラム販売の男性に対し著作権法・商標法違反で有罪判決(2017年8月30日)
「メルカリ」で違法複製プログラム等販売をした男性に対し、初の有罪判決(2017年12月22日)
また、摘発を逃れて法的リスクを負わずに済んだとしても、違法なコピーソフトの利用は、対外的な信用を失う恐れがある行為です。
企業の信用が失墜し、取引先や顧客の信頼を失うリスク
不正にコピーしたソフトを利用していることが明るみに出れば、社会的な信用を損なうでしょう。
企業コンプライアンスが厳格な会社の場合、違法な行為のある取引先との関わりを避ける可能性が高くなります。
新規受注の減少や契約解除、最終的に取引停止となる恐れがあります。
法的リスクを回避できても、会社業績に直結するリスクの可能性を忘れてはいけません。
求職者も、問題ある企業への就職は避けると考えられ、採用活動にも悪影響をおよぼすでしょう。
人手不足の解消や後継者育成に支障をきたし、企業の活動が停滞する原因となります。
従業員に「この会社で働いて大丈夫?」という不安が広がるリスク
コピーソフトの利用は新規採用する求職者だけでなく、既存の従業員からも不信感を抱かれる要因です。
違法性のある行為が常態化する環境で働くことにストレスを感じ、仕事へのモチベーションが低下すると考えられます。
黙認した自分自身も、違法行為に加担していると、葛藤や後悔の念を抱える従業員もいるかもしれません。
結果、離職につながり、良い人材を確保できないことにもつながります。
会社で違法なコピーソフトを見つけたときの対処法
不正にコピーされたソフトの利用は、さまざまなリスクがあり、その事実を知りながら働くのは心理的ストレスになり得ます。
では、自分が勤めている会社で違法なコピーソフトを見つけた場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
ここからは、違法なコピーソフトを見つけたときの対処法を解説します。
もし、現在の職場でコピーソフトの利用を知ってしまい、悩んでいる方の参考になれば幸いです。
また、企業体質が変わらないのであれば転職も視野に入れ、違法なコピーソフトを使う職場からは離れたほうが良いかもしれません。
まずは社内で相談できる人がいるか確認する
社内に相談できる上司やコンプライアンス担当者がいるなら、まずは正式なルートで相談してみましょう。
1人で対応するのは難しい場合もあり、一緒に考えたり、行動したりしてくれる存在があると安心です。
ただし、零細企業や家族経営の小さな会社では、社内に適した相談先がないこともあります。
上司も不正ソフトの利用を容認している様子なら、相談を持ちかけることで自分の立場が悪くなる恐れもあります。
そのような場合は、コピーソフトが使われている現状の証拠を保存し、外部の通報窓口を利用しましょう。
コピーソフトに関する証拠を残す
社内に相談出来る相手がいない、または相手がいても頼れそうにない場合は、外部に相談するための証拠を用意しましょう。
外部の通報窓口を利用しても、コピーソフトの利用を示す証拠がないと、思ったように動いてもらえない可能性があります。
客観的に状況を確認できる、スクリーンショットや使用履歴の画像などがあると有効です。
ただし、証拠を残すためであっても私的なコピーやソフトの持ち出しはおすすめしません。
あくまでも、業務中自然に得た範囲の記録にとどめるようにしましょう。
BSA(ソフトウェア事業者団体)など外部の通報窓口を利用する
違法なコピーソフトについて証拠を用意できたら、外部の通報窓口を利用して事実を伝えます。
Business Software Alliance(ビジネス ・ソフトウェア・ アライアンス/略してBSA)は、著作権保護に関する調査研究や啓発活動をしている機関です。
不正ソフトの報告窓口を用意し、職場で違法なコピーソフトの存在に気づいた場合も報告を付け付けています。
情報提供者が会社側に特定されない措置を講じているようで、会社バレの心配をせずにすみます。
ほかにも、一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(略してACCS)も、不正ソフトの情報を受け付けています。
改善が見込めないなら転職も視野に入れる
社内外の相談窓口・通報窓口を利用しても、違法なコピーソフトを利用する会社体質が好転するとは限りません。
行動を起こしたことで、自身は不正行為に加担するつもりはない、違法なソフトを認めてないという立場を取れるものの、会社自体が変わらなければ問題の根本が解決されません。
改善が見込めない職場に居続けるのが苦しく感じるならば、転職も選択肢となるでしょう。
転職を考えるなら、仕事内容や労働条件のほか、コンプライアンス意識の高い会社かどうかの確認が必要です。
転職先も同じように、違法なソフトの利用が常態化しているならば、環境を変える意味がありません。
企業のコンプライアンス意識は、外からは見えにくい部分ですが、口コミ情報やITリテラシーへの理解、ソフトウエアの管理体制などから判断しましょう。
まとめ
かつての経験をもとに、体験談を交えてコピーソフトを使う職場について書いてみました。
あの頃はただ周りに流され、状況を受け入れるしかできなかったのですが、今でも後悔する気持ちはあります。
こうしたモヤモヤを抱えないために、同じような状況に面している方がいるなら、参考になる記事を書いてみようと思った次第です。
不正にコピーされたソフトの利用は法律に反する行為ですが、悪気なく行なわれているケースも珍しくありません。
それゆえ、指摘しにくい状況もあると思われます。
BSAでは、不正コピーソフトの通報窓口を用意しているので、勤め先で該当する行為を見つけたなら利用すると良いでしょう。
通報者のプライバシーが守られるよう配慮されているため、会社側にバレて、立場が悪くなるのを避けられます。
また、違法な行為を行なう職場にいること自体が苦痛に感じるならば、転職も検討しましょう

事務歴十数年のたぬきです。
就職氷河期で苦しみ、合わない仕事に疲れ、転職して事務職に就くも会社倒産。再就職先がブラック体質で心を病み……持ち直して事務の派遣で仕事に復帰したのち直接雇用となるも、仕事量と給与のバランスに納得できず、組織に属することを諦めました。
現在、フリーライターとして死なない程度に生きてます。




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません