事務職だって業務改善!今すぐできる内容と取り組み時のポイントをご紹介
事務職の方は仕事のなかで「この業務フローは本当に必要?」「この作業って、二度手間じゃない?」などと、感じるシーンはないでしょうか?
業務フローを変更したり、システムを刷新したりして効率化を図ってほしくても、上司や会社の承認が必要な改善提案を通すのは困難です。
事務職で働くいち従業員が改善提案ても、なかなか理解を得られず、もどかしい思いをすることもあるでしょう。
事務職の方が業務改善を考えるなら、大がかりな内容よりも、個人の努力や工夫でできることに取り組むほうが、容易に達成できます。
この記事では、今すぐ取り組める、事務職の業務改善を取り上げます。
今日からできる!事務職の業務改善
業務改善と聞くと、大がかりな仕組みや制度の見直しをイメージするかもしれません。
しかし、業務改善は何も、大がかりなものに限りません。
身の回りのちょっとした工夫で、業務効率を高めることは可能です。
まずは、今日からでも取り組める事務職の業務改善をスタートしてみましょう。
結果を出し、成果を積み重ねることで自身の評価につながり、大きな改善提案をしても意見が通りやすくなります。
デスク周りを整理して動線を整える
業務改善として最初に見直したいのが、毎日使うデスク周りの整備です。
常に整理・整頓できていて、スムーズに業務を遂行できている方はその状態を維持しましょう。
しかし、よく使うファイルや文房具の位置がバラバラであったり、一緒に使用する資料が離れた場所に置いてあったりすると、業務をスムーズに行えません。
書類が積み上がった状態になっていては、必要なときに素早く取り出せず、探す手間がかかります。
このような状態だと、ちょっとした作業のたびに無駄な動きが生まれます。
自身の業務を見直し、各工程で何が必要かを把握して、使い勝手の良い位置に置くようにしましょう。
その際、使用頻度や重要度に合わせた置き場所決めが重要です。
使用頻度の高い書類は、すぐ手の届く場所に置きたいところですが、内容によっては鍵のかかる場所に保管する必要があるでしょう。
パソコンのデスクトップを整理する
デスク周りと同様に、パソコンのデスクトップ画面も整理しておきましょう。
保存したファイルやショートカットで、デスクトップが埋め尽くされていないでしょうか?
すぐにアクセスできて便利に感じるかもしれませんが、どれが必要なデータかわかりにくくなることもあります。
自分は毎日使っているから、何が・どこにあるかを把握できている、という方もいるかもしれません。
しかし、他の人にとってはそうではありません。
休みを取った際、誰かが代理で対応する必要があるとき、デスクトップが散らかっているとスムーズに作業できないでしょう。
パソコンのデスクトップには基本的にデータを保存せず、保存する場合は一時的な置き場所として使いましょう。
デスクトップからすぐにアクセスしたいデータは、ショートカットを作り、デスクトップに貼り付けます。
ショートカットもむやみやたら増やさず、使用頻度の高いものを厳選しましょう。
業務の種類ごとにフォルダー分けして、フォルダーのなかにショートカットを格納する方法もあります。
デスクトップ画面をスッキリした状態にしておけば視認性が上がり、他の人が操作することになってもスムーズに使用できます。
データ保存時の保存場所とファイル名をルール化する
データを入力したり、書類を作成したりと、事務職の仕事ではさまざまなデータファイルを扱います。
では、それらのデータファイルを保存する際、場所やファイル名の付け方をルール化できているでしょうか?
残念ながら、どこに・どのように保存するか決まっていないケースも珍しくありません。
このような状態だと、業務が属人化する可能性があります。
保存場所やファイル名のルールがあいまいで、場当たり的に処理していると、後から探し出すのが難しくなります。
急な休みや引き継ぎが発生した際、他の人では対応できなくなる恐れもあるでしょう。
保存場所とファイル名のルールを明確にし、誰が見てもわかりやすい状態にしておくことも、業務効率を高めます。
たとえば、業務内容ごとにフォルダで分けて保存し、ファイル名は「日付+作業内容+対応者」にしておくと、のちのちデータを探す際も見つけるのが容易です。
作業の途中から引き継ぎもしやすくなり、業務の属人化を防げます。
固有名詞や定型文をユーザー辞書に登録する
特定分野では頻出する用語だが一般的ではない言葉、略称、難読漢字などは、漢字変換がスムーズにできないこともあります。
長いカタカナ表記の社名やサービス名などは、入力ミスを招く存在です。
これらの小さなストレスは、ユーザー辞書の活用で解決できます。
登録の手間はありますが、一度登録すれば、以降は入力の手間が軽減し、作業スピードをアップできます。
ほかにも、良く使う文言があるなら、辞書登録がおすすめです。
たとえば、メール送信の機会が多く、メール本文の冒頭に「お疲れ様です」や「お世話になっております」などの一文を良く使うなら、ユーザー辞書に登録してしまいましょう。
フォーマット・テンプレートを作成する
作成頻度の高い書類やメールは、毎回いちから作成するより、テンプレート化したほうが効率的です。
見積書や請求書、プレゼン資料、挨拶文など、形式が決まっているものは雛形を作って登録しておきましょう。
テンプレートを作らなくても、過去に作成した同種のファイルを複製し、必要な箇所のみ修正する方法もあります。
しかし、この方法では修正漏れが発生した際にリスクがあるため、良い方法とは言えません。
たとえば、顧客Aに提出する見積書を作成するため、過去に作った顧客B宛の見積書を複製したとします。
見積内容は顧客Aの依頼に添うよう修正したものの、見積書の表に記載する宛名の修正が漏れているとどうなるでしょうか?
宛名が顧客Bの名称になっている状態で、顧客Aに見積書を提出することになります。
顧客Aに対して失礼なだけでなく、顧客Bの存在を顧客Aに知られてしまいます。
他の顧客の存在やそれが誰であるかを知られることは、必ずしも問題ではありません。
しかし、場合によっては顧客Aからの心証を悪くする恐れがあります。
あるいは、他の人に見積書の提出を依頼した際、宛名として記載された顧客Bのところに届けられてしまうかもしれません。
肝心の顧客Aには見積書が届かず、顧客Bは頼んでもいない見積書を受け取る結果となります。
こうしたミスを防ぐには、最初から必要項目を空欄にしたテンプレートを用意するほうが安全で確実です。
ショートカットキーを活用する
データの保存、ひとつ前の操作を取り消し、コピー&ペーストなどを行なうとき、マウス操作よりもキーボードのショートカットキーを使うと作業スピードを高められます。
いちいちマウスの右クリックから操作を呼び出したり、画面上のアイコンをクリックし行ったりせずに済むため、キーボードから手を離す必要がありません。
キーボードとマウスはどちらも必要な入力装置ですが、作業効率を上げるなら、ショートカットキーの活用も重要です。
ショートカットキーは膨大な数が存在しますが、実用的なものから少しずつ覚えて行きましょう。
関数やマクロなどを活用する
Excelなどの表計算ソフトを使う場面が多いなら、関数やマクロを活用しましょう。
関数は数値の集計だけでなく、特定の文字列を追加・抜き出し、行・列の入れ替え、条件にあてはまるデータの抽出などもできます。
上手く使えるようになれば、既存データからほしいデータ形式への修正も容易にできるようになります。
- IF関数(IF、SUMIF、COUNTIF、AVERAGEIFなど)…条件を指定した抽出や計算ができる
- VLOOKUP…リストの指定範囲内から該当データを取り出す
- CONCAT…指定範囲の文字列を結合して表示する
「IF関数」で条件別の対応を設定したり、「VLOOKUP」で情報を引き出したりすることで、手作業を減らせます。
さらに、定型的な繰り返し作業が多いなら、マクロを使って操作順序を記録すると処理の自動化が可能です。
関数やマクロの活用と聞くと、最初は難しく感じるかもしれませんが、使えるようになればパソコンスキルがアップします。
簡単なところから学び、業務に取り入れると、作業効率の向上や自身のスキルアップを感じられるでしょう。
事務職の仕事にやりがいがないと感じていたり、事務職の目標設定に悩んだりしているなら、関数の活用術やマクロを学習してスキルアップするのもおすすめです。
業務マニュアルを作成する
業務の手順をマニュアルとしてまとめておくと、急な引き継ぎや代理対応が発生しても、スムーズに対処できます。
マニュアルの作成には時間がかかりますが、手順を文章化する過程では業務フローの見直しもできます。
業務改善すべき問題点を洗い出せるでしょう。
なお、マニュアルは余裕のある時期に少しずつ進めるのがコツです。
繁忙期や優先業務のある時期に取り組むのは避け、仕事が立て込んでいないときに作成を進めましょう。
事務職が業務改善に取り組む際のポイント
紹介してきた業務改善のアイデアは、すぐに実践できるため、早速試したいと思う方も居るでしょう。
しかし、実行するタイミングや関係者との連携など、配慮すべき問題もあるため、いつでも始められるとか限りません。
無理なく、効果的に業務改善を進めるため、以下で紹介するポイントを押さえましょう。
チーム内で足並みを揃える
複数人のチームで事務業務を担っている場合、業務改善は「個人プレー」ではなく「チーム戦」として進めましょう。
良い業務改善であっても、勝手な変更を加えると混乱を招いたり、周囲の反感を買ったりする原因です。
データ保存時のルールは、チーム内で共有しなければ効果を得られません。
他の人も利用するユーザー辞書の登録情報やテンプレートの作成・整備は、意見を出し合って整えたほうが、より良い状態にできるでしょう。
チームの協力を得て業務改善を進めたほうが、より効果的な業務改善につながります。
繁忙期に大がかりな取り組みは避ける
業務改善は通常業務に支障が出ないよう、取り組む時期を考えることも重要です。
業務改善は「本業をよりスムーズにするための手段」であり、忙しい時期に優先して取り組むべきではありません。
「今やるべきか?」「今やっても無理なく続けられるか?」という視点を忘れず、優先順位を考えて進めましょう。
業務改善を目標設定に組み込む
業務改善に取り組むなら、ぜひ目標設定の中に組み込みましょう。
「〇〇の処理時間を10分短縮する」「△△の作業ミスをゼロにする」といった、具体的な目標があると意識を高められます。
上司に業務改善の計画や進捗を報告すれば、目標と達成状況がわかりやすく伝わり、評価アップにもつながります。
成果を数字に表わしにくい事務職において「改善に取り組んだ」「このような効果が出た」といった具体的な内容を伝えられると、アピールとして効果的です。
さらに、目標達成による達成感は、日々の業務に対するやりがいやモチベーションの向上にも直結します。
今すぐ始める事務職の業務改善がもたらす変化
事務職の仕事は、目に見える成果が出にくい部分がありますが、業務改善に取り組むことで成果を見える化できます。
さらに、日々小さな変化を積み重ねることで、働き方や意識、周囲との関係にも、良い影響が広がるでしょう。
時間と心にゆとりが生まれる
業務改善に成功すると、時間や心にゆとりをもたらします。
無駄な手順の削減やスムーズな業務進行で、毎日の仕事が円滑なものになるでしょう。
たとえば、保存データをルール化して整理したり、利用頻度の高いテンプレートを活用したりすると、作業時間が短縮できます。
時間短縮できた分、ほかの業務に取り組むゆとりが生まれ、繁忙期の残業削減にも効果的です。
「やらなければ」と、常に気になる作業が効率化されると、心理的なストレスも軽減されるでしょう。
時間と心に余裕ができれば、視野も広がります。
さらなるスキルアップや信頼獲得につながるアクションもできるようになり、自身の成長につながります。
「見える努力」として信頼・評価につながる
事務職の仕事は、結果が数字に現れにくいため、何に努力したかを伝えるのが難しい状態です。
業務改善に取り組み、努力や工夫を“見える形”で表現できれば、頑張りが伝わりやすくなるでしょう。
作業効率の向上から、同僚や上司から感謝の声が寄せられれば、自身のモチベーションも高まります。
さらに、目に見える貢献があることで、職場での信頼感を高め、人事評価にも好影響を及ぼす可能性があります。
成果をアピールしづらい事務職にとって、業務改善は「貢献の見える化」に役立つ手段です。
やりがい・成長実感がキャリアにも活きる
改善を積み重ねて業務がスムーズに進行し、周囲からの評価されるようになれば、自信ややりがいを感じる場面が増えるでしょう。
「自分の工夫で職場が良くなった」と実感できれば、自然と前向き気持ちで仕事に取り組めます。
こうした経験は、中長期的なキャリアを考えた際にも効果があります。
パソコン操作の効率化やマニュアル作成のスキルは、汎用性の高いスキルです。
業務改善の取り組みを通じて身につけたスキルは、キャリアアップを考える際にも役立ちます。
そして、改善実績は、転職活動をする際に具体的なアピールポイントとして語れる材料です。
「今の職場では評価されにくい」「事務職はやりがいがない」と感じている方は、業務改善を積み重ねる効果に目を向けましょう。
まとめ
事務職の業務改善は、大がかりなものに限りません。
日々のちょっとした工夫から始められることも多いため、できるところから始めてみましょう。
まずは自身が担当する作業を見直し、効率化できる部分がないか探すところがスタートです。
作業がスムーズにできるよう、環境を整え、必要なスキルを身につけることで、業務改善につながります。
小さな改善でも、積み重ねるにつれて時間と心の余裕を生み、やりがいや評価にもつながります。
紹介したアイデアや進め方を参考に、ぜひ「できること」から取り組んでみてください。

事務歴十数年のたぬきです。
就職氷河期で苦しみ、合わない仕事に疲れ、転職して事務職に就くも会社倒産。再就職先がブラック体質で心を病み……持ち直して事務の派遣で仕事に復帰したのち直接雇用となるも、仕事量と給与のバランスに納得できず、組織に属することを諦めました。
現在、フリーライターとして死なない程度に生きてます。


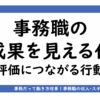
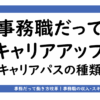
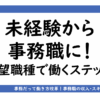
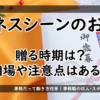
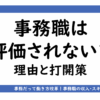
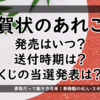

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません